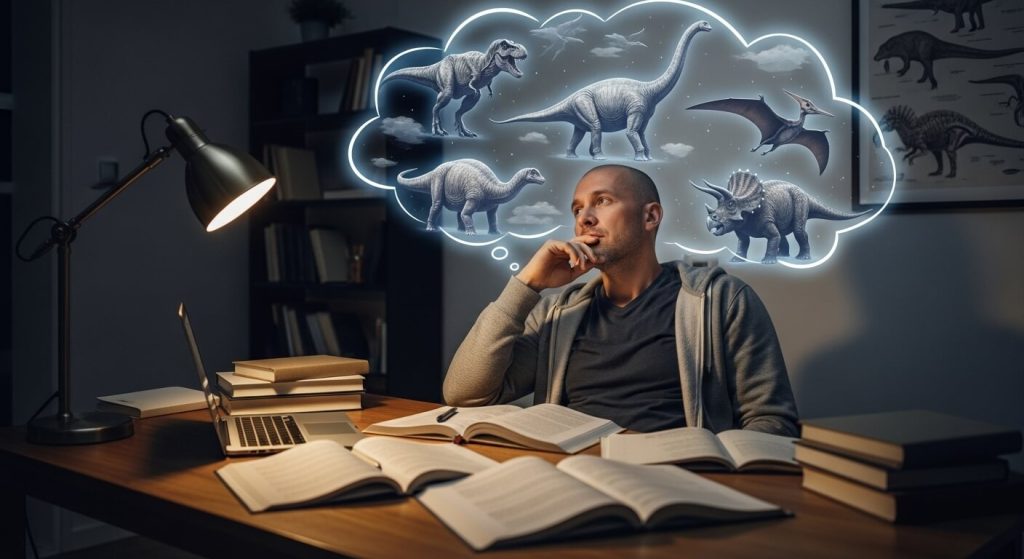
mesozoniaオリジナルイメージ
恐竜学検定に興味があるけれど、以前なくなったという話を聞いて戸惑っていませんか。
あるいは、どのような検定で、どんなメリットがあるのか、具体的な学習方法が分からず一歩を踏み出せないでいるかもしれません。
この記事では、そんな疑問を解消するため、復活した恐竜学検定の概要から、受験するメリット、合格に向けた具体的な学習方法まで、網羅的に解説していきます。
検定の全体像を掴み、恐竜の知識を深める挑戦への一歩を踏み出しましょう。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
・検定の具体的な概要や受験するメリット
・合格に向けた効果的な学習方法とコツ
・子どもから大人まで楽しめる検定の魅力
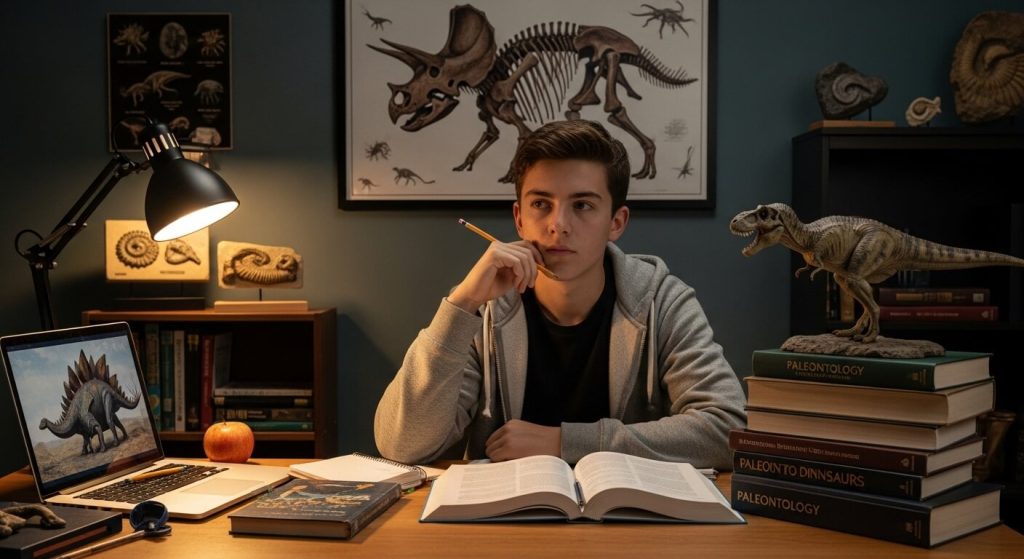
mesozoniaオリジナルイメージ
恐竜学検定とは?基本情報を網羅解説
この章では、恐竜学検定がどのような試験なのか、その基本的な情報について詳しく見ていきます。
- 恐竜検定はなくなった?という噂の真相
- 現在の恐竜学検定の概要と主催団体
- 受験資格や難易度はどうなってる?
- 合格基準と合格率の目安は?
- 受験者全員がもらえる特典を紹介
- 恐竜学検定を受けるメリットを解説
恐竜検定はなくなった?という噂の真相
「恐竜検定はなくなった」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは半分正しく、半分は誤解です。
過去には「動物検定/恐竜検定」や、福井県立恐竜博物館が監修した「全日本恐竜検定」といった検定が実施されていました。しかし、これらの検定は現在では行われていません。
一方で、恐竜ファンの熱い要望に応える形で、2024年に「第1回恐竜学検定」が新たにスタートしました。
この検定は大きな成功を収め、2025年にも第2回が開催されるなど、現在は「恐竜学検定」という新しい名称で定期的に実施されています。
したがって、恐竜の知識を試す機会がなくなったわけではなく、新たな形で続いているのが現状です。
現在の恐竜学検定の概要と主催団体
現在実施されている恐竜学検定は、日販セグモ株式会社が企画・運営しています。
そして、監修は日本の恐竜研究の第一人者として世界的に知られる、小林快次先生(北海道大学総合博物館教授)が務めています。
この検定は、公式サイトで「未だその生態に謎が多い『恐竜』。彼らが生きていた太古の時代に想いをはせ、恐ろしくも神秘的な、恐竜の真実へと挑戦する検定です。」と紹介されており、専門的な知見に基づいた質の高い内容であることがうかがえます。
検定の基本情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検定名称 | 恐竜学検定 |
| 主催 | 日販セグモ株式会社 |
| 監修 | 小林快次(北海道大学総合博物館教授) |
| 等級 | 初級、中級 |
| 受験資格 | 年齢、経験、国籍を問わず、誰でも受験可能 |
| 試験形式 | 4者択一のマークシート方式(100問) |
| 公式サイト | 公式ウェブサイトで最新情報を確認可能 https://www.kentei-uketsuke.com/dinosaurs/ |
受験資格や難易度はどうなってる?
恐竜学検定の大きな特徴の一つは、受験資格に一切の制限がない点です。
年齢やこれまでの経験、国籍などを問わず、純粋に「恐竜が好き」という気持ちがあれば、子どもから高齢の方まで誰でも挑戦できます。
実際に、第1回検定の受験者データを見ると、小学生以下の受験者が全体の44%を占めており、非常に幅広い年代に支持されていることが分かります。
難易度については、現在「初級」と「中級」の2つのレベルが設定されています。
初級は恐竜の基本的な知識を問う内容で、これから学び始める方や子どもたちに適しています。
一方、中級はより専門的で幅広い知識が求められるため、長年の恐竜ファンや大人でも十分に手応えを感じられる内容になっています。
決して子ども向けの簡単な検定というわけではなく、各レベルに応じた知識の深化が求められます。
合格基準と合格率の目安は?
恐竜学検定の合格基準は、初級・中級ともに、おおむね正答率70%以上とされています。
問題形式は、4つの選択肢から1つを選ぶマークシート方式で、問題数は100問です。
ただし、主催者から公式な合格率は公表されていません。
第1回検定では全国で約7,000名が受験したと発表されており、その中で多数が合格していると考えられます。
検定の目的が知識を競うことだけでなく、恐竜への興味関心を深めることにもあるため、極端に低い合格率にはなっていないと推測されます。
公式ガイドブックなどを活用してしっかりと対策を行えば、合格の基準をクリアすることは十分に可能と考えられます。
受験者全員がもらえる特典を紹介
この検定が多くのファンを惹きつける理由の一つに、魅力的な特典の存在が挙げられます。
まず、受験を申し込んだ方全員に、検定限定のオリジナルグッズがプレゼントされます。
例えば、第2回検定では、ティラノサウルスのデザインが施されたクリアフォトカードが特典として用意されました。
さらに、見事合格基準を突破した方には、特別な合格認定証が贈られます。
この認定証は、人気恐竜・古生物イラストレーターのケータさんがデザインを手がけたもので、自分の名前が入った世界に一つだけのオリジナルデザインです。
こうした記念に残る特典は、学習のモチベーションを高める大きな要因となっています。
恐竜学検定を受けるメリットを解説
恐竜学検定を受験することには、知識の証明以外にも様々なメリットが存在します。
知識の体系的な深化と再確認
最大のメリットは、恐竜に関する知識を体系的に深められる点です。なんとなく知っていた断片的な情報が、検定の学習を通じて整理され、より深く、正確な知識へと昇華します。また、最新の学説に触れる良い機会にもなり、恐竜への興味や探究心をさらに刺激してくれるはずです。
学習意欲の向上と親子のコミュニケーション
「合格」という明確な目標を持つことで、学習へのモチベーションが高まります。特に恐竜好きの子どもにとっては、遊びの延長線上で知的好奇心を満たせる絶好の機会です。また、親子で一緒に挑戦すれば、共通の話題でコミュニケーションが深まり、楽しみながら学ぶ素晴らしい体験となるでしょう。
注意点
一方で、注意点として、この検定はあくまで趣味や教養の範囲の知識を問うものであり、直接的な就職やキャリアアップに結びつく資格ではないという点が挙げられます。しかし、博物館の解説員や関連イベントの企画など、将来の可能性を広げる一つのきっかけになるかもしれません。

mesozoniaオリジナルイメージ
恐竜学検定の合格に向けた対策と学習法
この章では、検定に合格するために、具体的にどのように学習を進めていけば良いのか、その方法とコツを解説します。
- 推奨される公式テキストでの学習方法
- 図鑑の活用など効果的な勉強のコツ
- 主な出題範囲と覚えるべきポイント
- 併願受験や見守り受験制度について
推奨される公式テキストでの学習方法
恐竜学検定の対策を始める上で、何よりもまず準備すべきなのが『恐竜学検定公式ガイドブック 初級・中級』です。
これは検定の主催団体が公式に出版しているテキストであり、検定問題の多くがこのガイドブックの内容に沿って出題されます。
言ってしまえば、合格を目指す上での必須アイテムです。
基本的な学習方法としては、このガイドブックを繰り返し読み込み、練習問題を解くことが中心となります。
特に、一度間違えた問題は、なぜ間違えたのかを解説でしっかり理解し、関連するページを読み返すことが大切です。
また、Kindleなどの電子書籍版も販売されているため、スマートフォンに入れておけば、通勤・通学などの隙間時間を活用して手軽に学習を進めることができ、効率的です。
図鑑の活用など効果的な勉強のコツ
前述の通り、公式ガイドブックが学習の中心となりますが、より高得点を目指す、あるいは中級に挑戦する場合には、公式参考図書である『学研の図鑑LIVE 恐竜 新版』の活用が鍵となります。
効果的な勉強のコツは、ガイドブックと図鑑を連携させて学習を進めることです。
例えば、ガイドブックで初めて見る恐竜や、特徴が覚えにくい恐竜が出てきた際に、すぐに図鑑でその姿や生息環境のイラストを確認します。
文字情報だけでなく、ビジュアルで捉えることで、記憶に定着しやすくなります。
一度調べた恐竜のページに付箋を貼っておけば、自分だけの弱点ノートのようになり、後から効率的に復習できます。
図鑑には持ち運びに便利なポケット版もあるため、外出先での学習にも役立ちます。
主な出題範囲と覚えるべきポイント
出題範囲は広範にわたりますが、合格ラインである7割以上の正答を目指すためには、以下の3つの基本ポイントを重点的に押さえることが効果的です。
- 恐竜の名前とその由来 恐竜の名前を覚えるのは基本ですが、なぜその名前が付けられたのか(例:「ティラノサウルス・レックス」=暴君のトカゲの王)という由来までセットで覚えると、忘れにくくなります。
- 発掘地、生きていた時代 どの恐竜が、どの時代(三畳紀、ジュラ紀、白亜紀)に、どの地域(大陸)に生息していたのかを関連付けて覚えることが求められます。地名が名前に含まれる恐竜(例:フクイラプトル)もいるため、ヒントになります。
- 恐竜の特徴(大きさ、食性、分類など) その恐竜がどのような姿をしていたのか、全長や体重はどれくらいか、何を食べていたのか(肉食・草食)、そして竜盤類・鳥盤類のどちらに分類されるか、といった具体的な特徴を正確に把握しておく必要があります。
併願受験や見守り受験制度について
恐竜学検定には、様々な人が受験しやすいように、いくつかの特別な制度が設けられています。
併願受験
初級と中級、両方のレベルに挑戦したい方向けの制度です。それぞれを個別に申し込むよりも割引価格が適用されるため、知識に自信のある方や、一度に両方のレベルを制覇したい方におすすめです。
見守り受験
一人で試験会場にいるのが不安な小さな子どもでも安心して受験できるよう、保護者が試験に同伴できる制度です。この制度では、保護者は試験問題に口出しすることはできませんが、すぐ隣で静かに見守ることができます。また、2人で協力して1つの解答用紙を完成させるペア受験も可能です。
これらの制度の受験料は通常とは異なるため、申し込む際には公式サイトで最新の情報を必ず確認してください。
| 受験スタイル | 初級 | 中級 | 併願(初級+中級) |
|---|---|---|---|
| 通常受験 | 4,600円 | 5,800円 | 9,800円 |
| 見守り受験 | 6,900円 | 8,700円 | 14,700円 |
| ※上記は第2回検定の税込み価格です。 |
まとめ:知識を深める恐竜学検定
この記事では、恐竜学検定の概要からメリット、具体的な学習方法までを詳しく解説してきました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。
- 恐竜検定は「恐竜学検定」として新たに開催されている
- 主催は日販セグモ株式会社、監修は小林快次先生
- 受験資格に制限はなく子どもから大人まで誰でも受験可能
- 難易度は初級と中級の2レベルが設定されている
- 合格基準はおおむね正答率70%以上
- 公式な合格率は公表されていない
- 受験者全員にオリジナルグッズの特典がある
- 合格者には名前入りの特製合格認定証が贈られる
- メリットは知識を体系的に深められること
- 学習意欲の向上や親子の交流にもつながる
- 対策には公式ガイドブックが必須
- 公式参考図書の図鑑を併用すると学習効果が高まる
- 名前の由来、時代、特徴が覚えるべき主要ポイント
- お得な併願受験制度がある
- 親子で安心の見守り受験制度も用意されている

